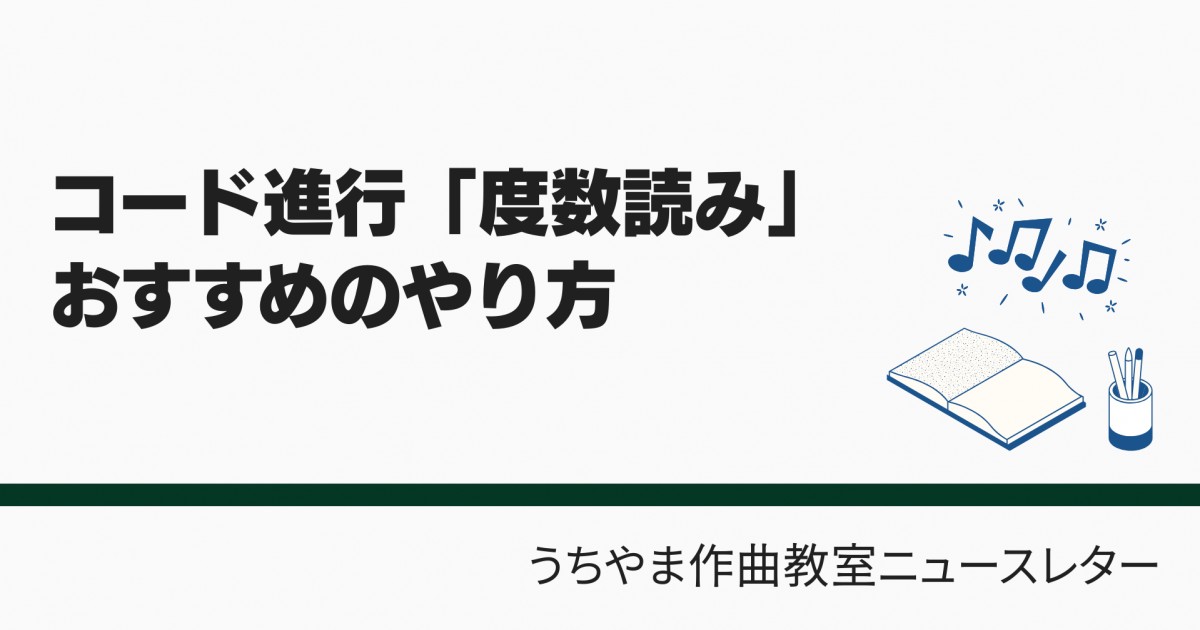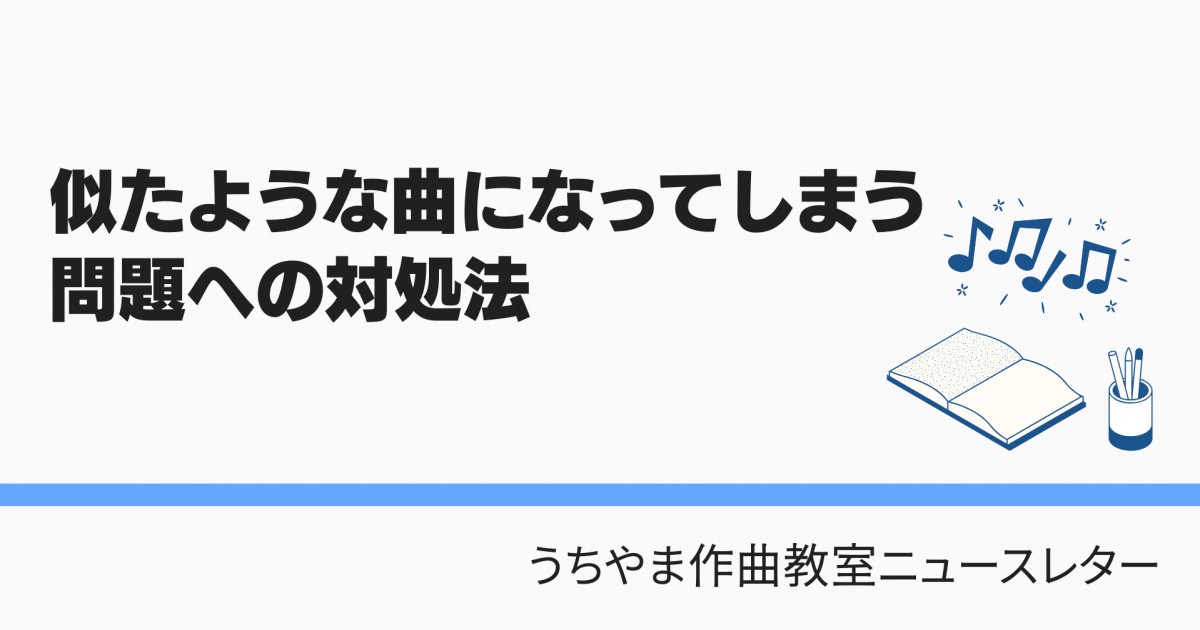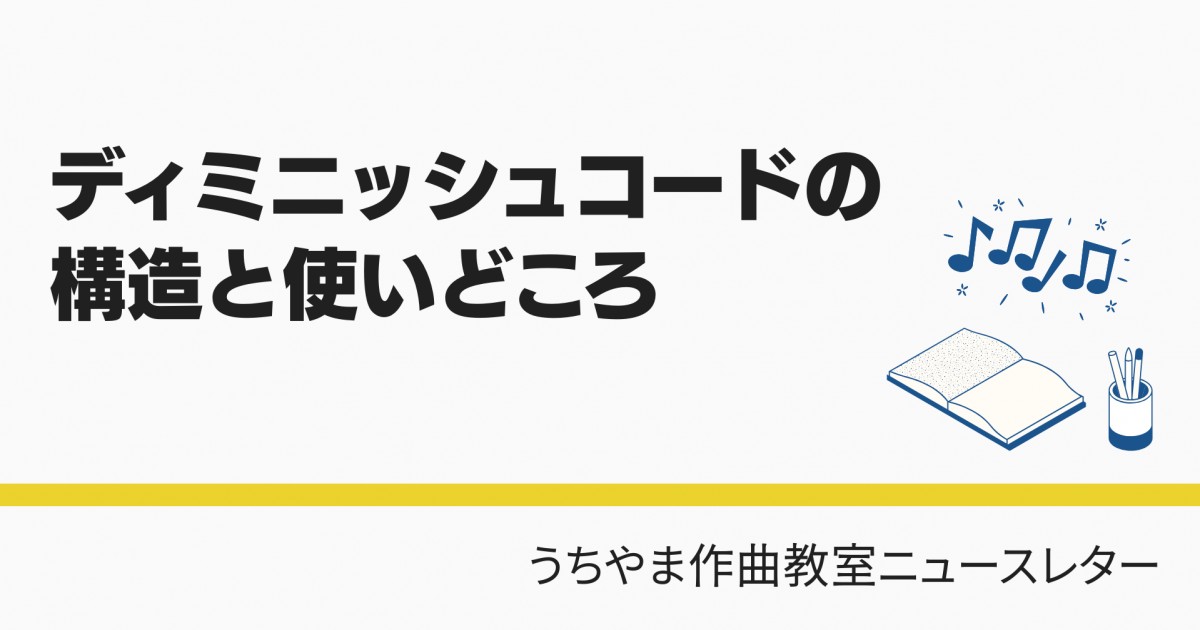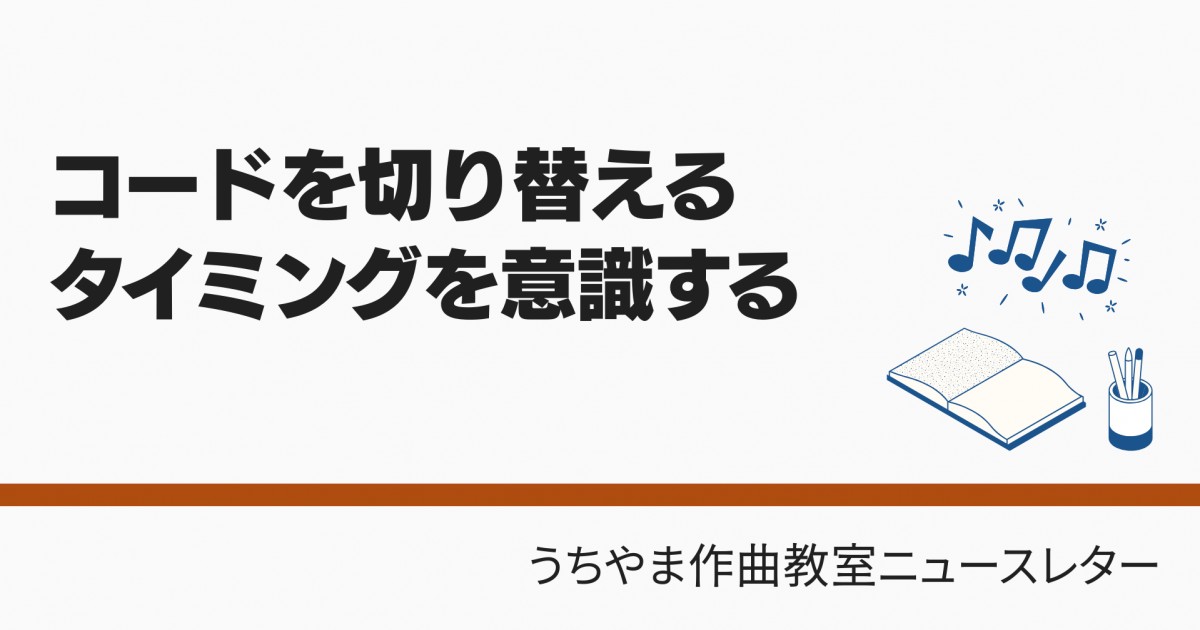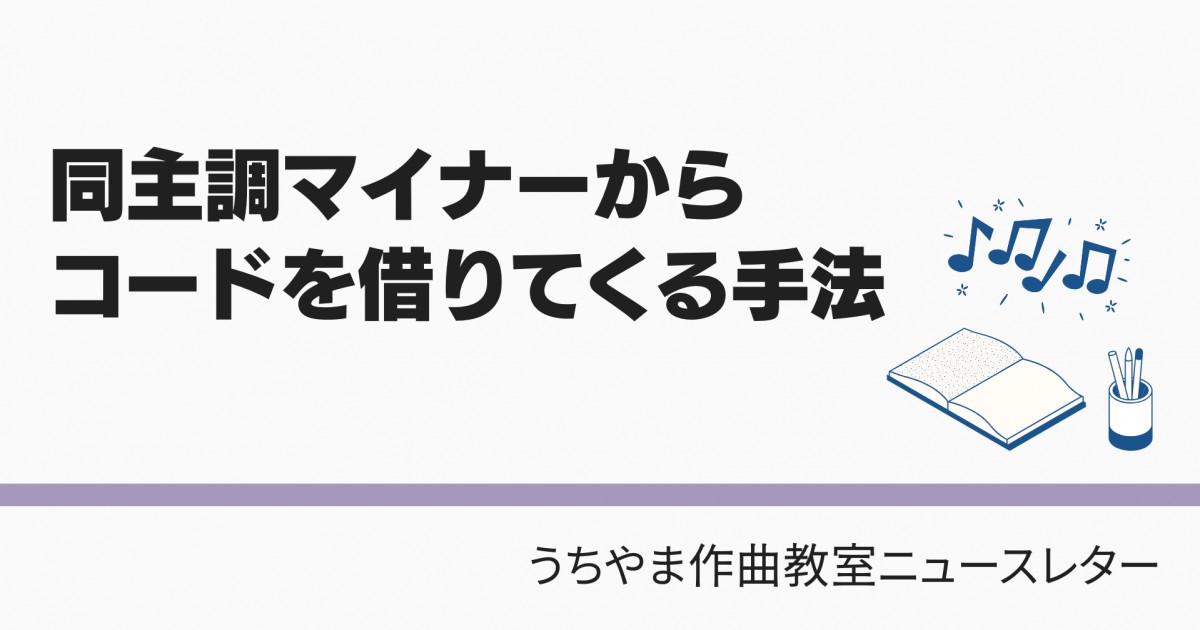カノン進行でハーモニー感覚を磨く
ポップス・ロックにおける定番のコード進行である「カノン進行」の概要と、応用例、有名曲における実例などをご紹介します。あわせて「似たようなメロディばかりになってしまう」という悩みへの見解などについてまとめています。
内山敦支
2024.10.23
読者限定
「カノン進行」について
作曲初心者にとって「定番のコード進行(=よくあるコードの展開)」は、ハーモニーの移り変わりやその構造を理解するのに役立ちます。
私は、実際の作曲でコード進行だけを先にすべて決めてしまうことをあまりおすすめしていませんが、特に作曲に慣れていないうちはそのような『コード進行の型』を楽曲の一部に取り入れることで、効率よく作曲の感覚を磨けるとも考えています。
この記事は無料で続きを読めます
続きは、6624文字あります。
- 「似たようなメロディばかりになってしまう」という悩み
- 「Kindle Unlimited」で音楽本に触れ続ける
- 編集後記
すでに登録された方はこちら