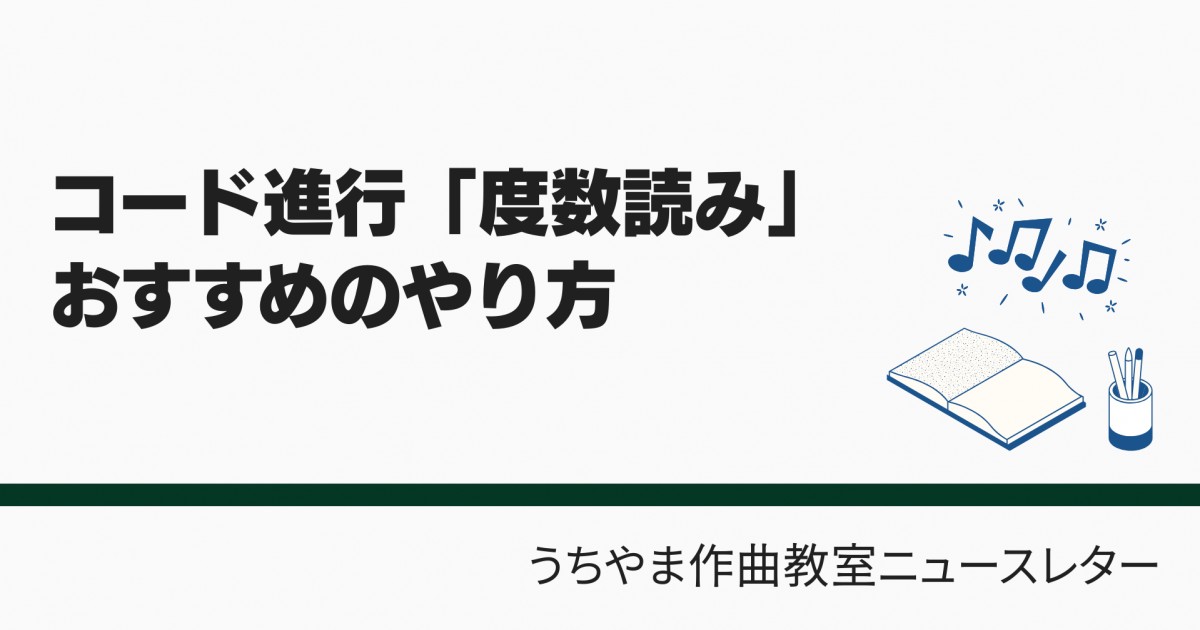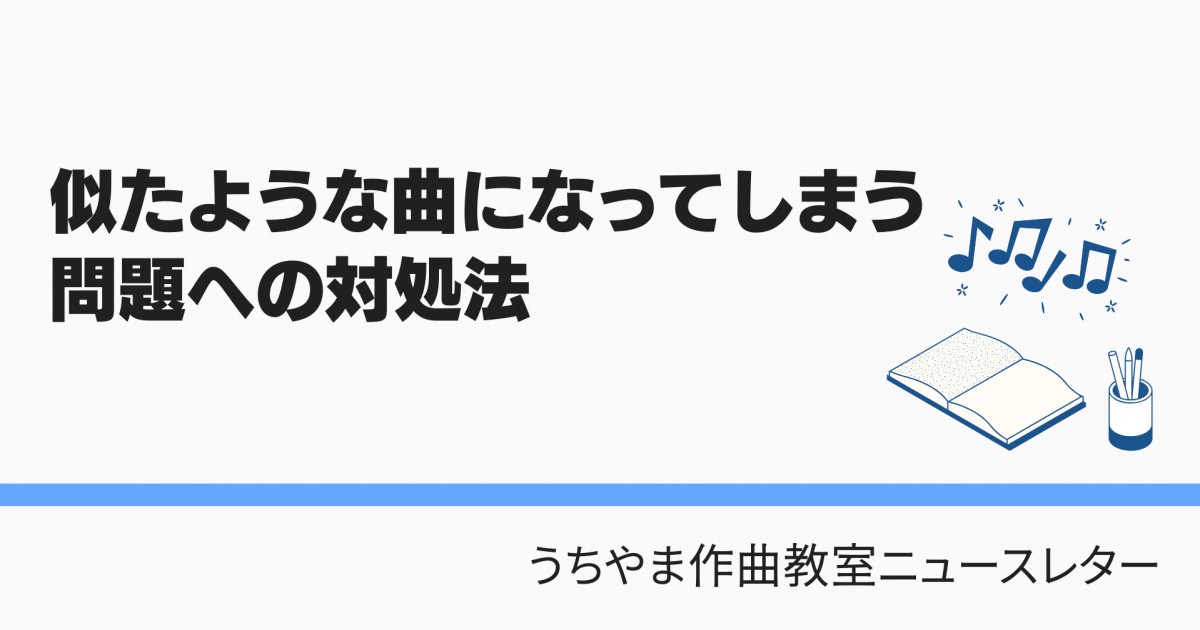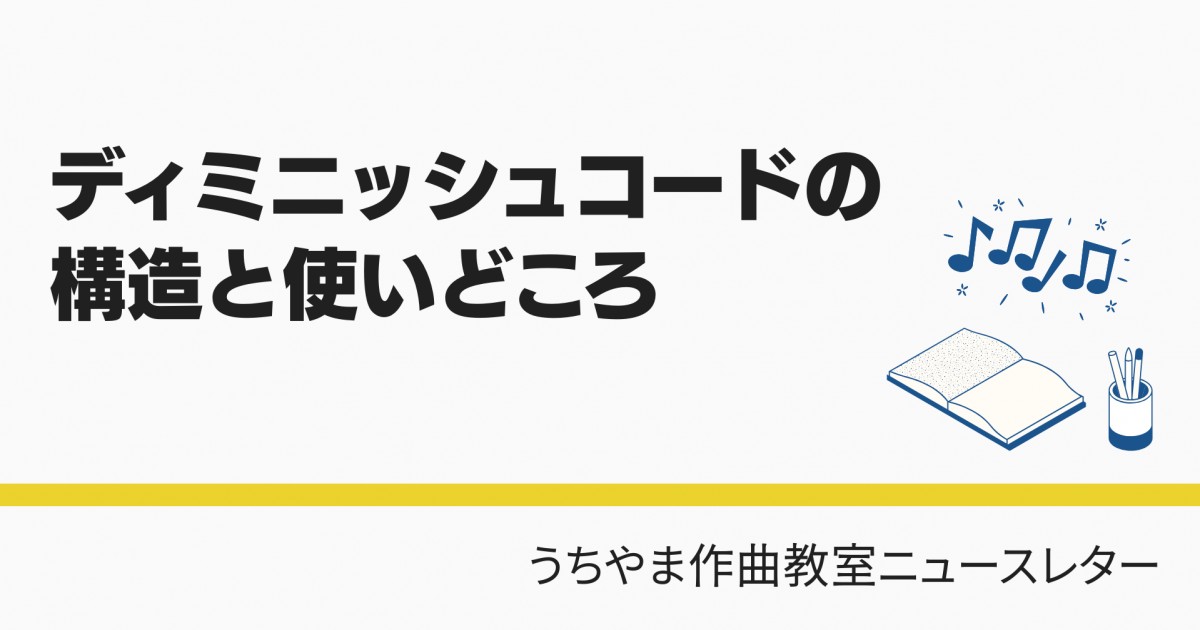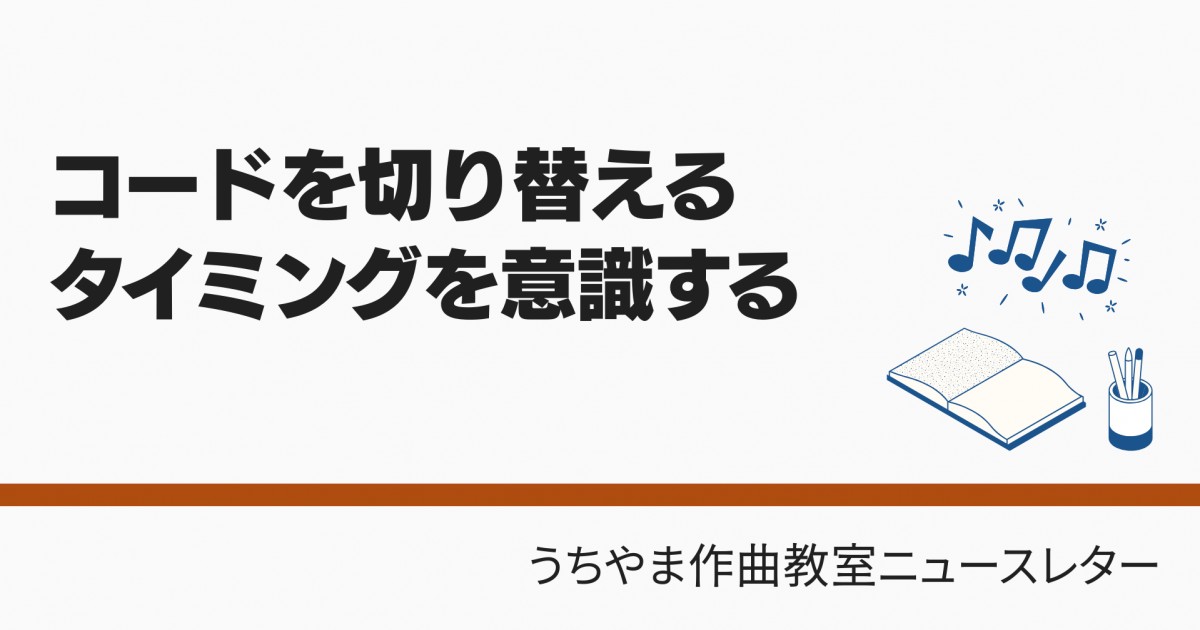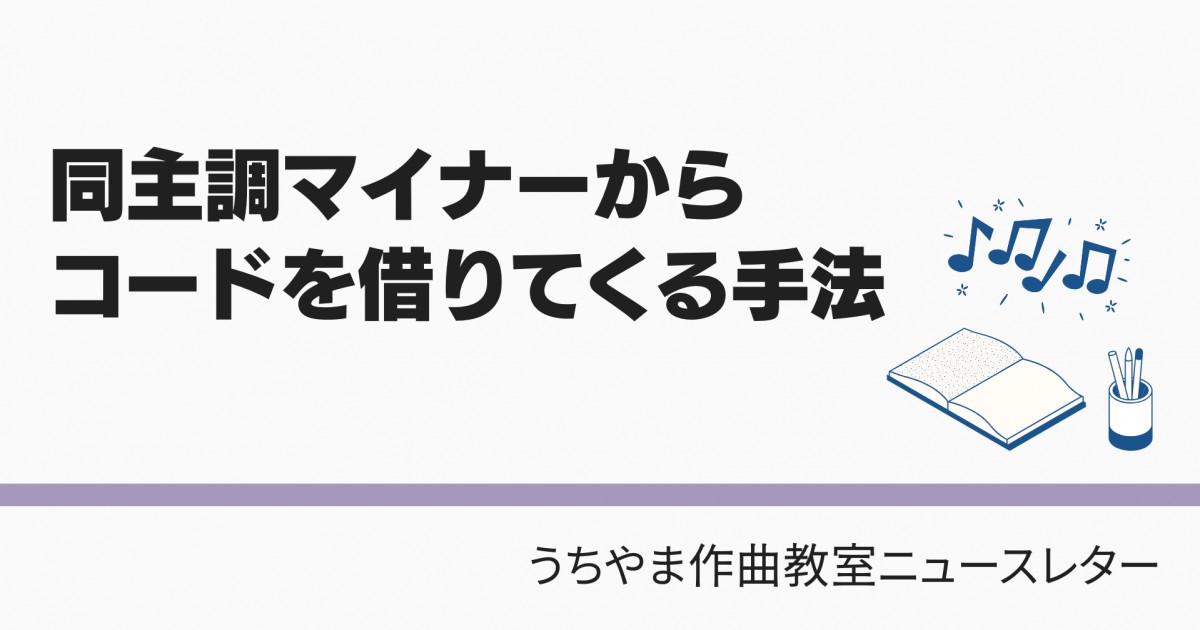メロディの質を高める「始め方」の概念
こんにちは。良いメロディを構造的に分析したくなってしまう内山です。
今回は、メロディの聴こえ方を左右する大事な概念ともいえる「メロディの始め方」について書きます。
メロディを作る上では音使いやリズム、音の進め方などいろいろな点に意識を向けることができますが、その中で特にメロディ作りに慣れていない人が見落としがちなのが「メロディの始め方」です。
当然のことながら、展開していくメロディはまず何らかのきっかけによって始まることになります。
さらには曲全体を通して見ても、全く切れ目がなくいつまでもつながり続けるようなメロディはなく、長く続くメロディも必ずどこかでその都度途切れることになるため、厳密にいえば特定のフレーズはその都度「始まっている」とも解釈できます。
セクション冒頭におけるメロディの始め方
ここではまず「Aメロ」「サビ」などのセクションの冒頭におけるメロディの始め方を前提として、どのようなパターンが想定できるかを整理します。
そもそも、メロディの始め方は大きく三種類に分けられます。具体的には、セクション冒頭を開始点としたうえで、
-
セクション冒頭よりも「前から」始まるメロディ
-
セクション冒頭と「同時」に始まるメロディ
-
セクション冒頭よりも「後から」始まるメロディ
の三種類です。
それぞれの状態を、図として分かりやすく示すと以下のようになります。

一般的に「前から」のメロディは、そのセクションの開始点を先取りするような効果を生むため、メロディに勢いがつくように聴こえます。
また「同時」のメロディは、セクション開始点と同じタイミングでアクセントが揃うため、そのセクションの始まりがより際立って聴こえ、場面転換がはっきりします。
「後から」のメロディは開始点に空白が盛り込まれることになるため、メロディから余裕がある雰囲気が生まれたり、アクセントがずれるような面白さが感じられたりします。