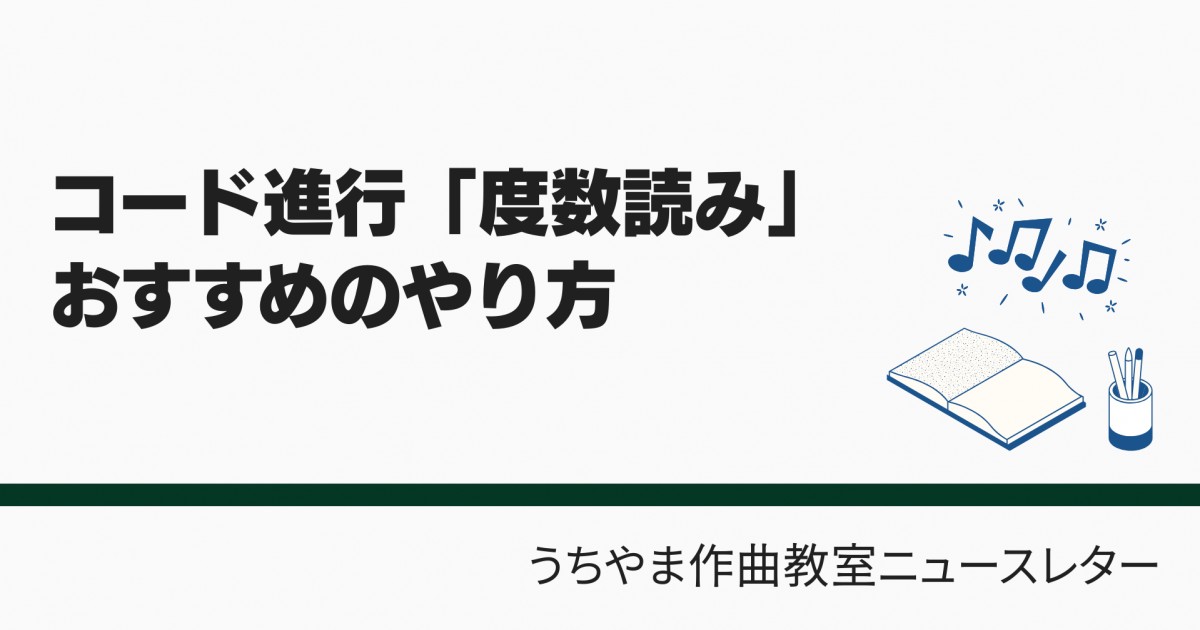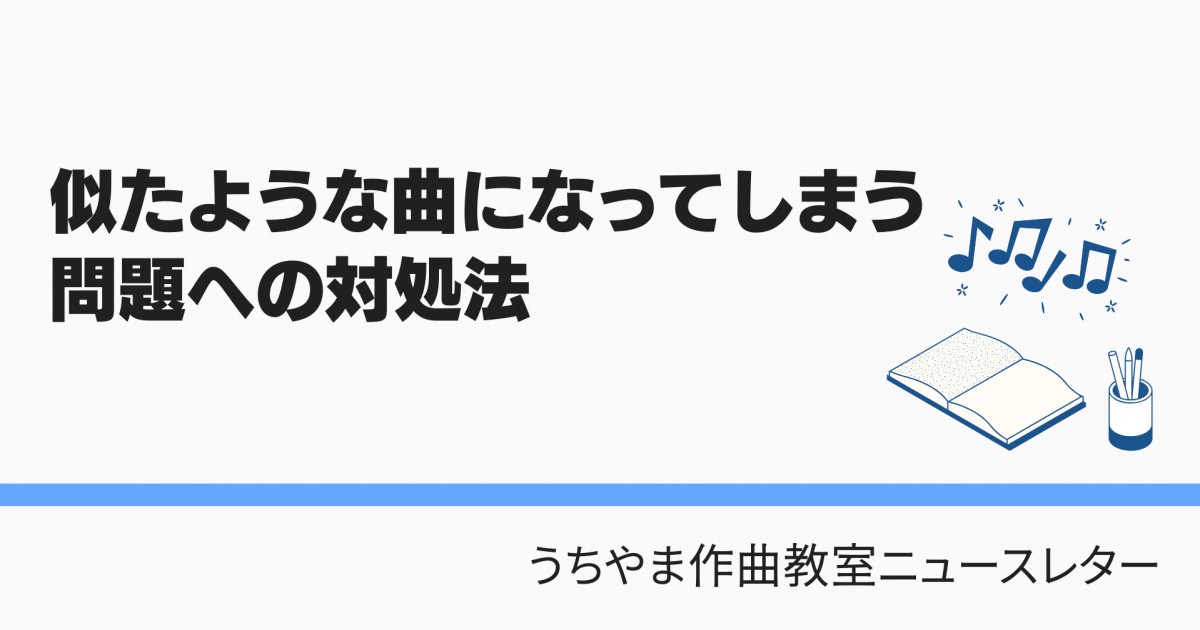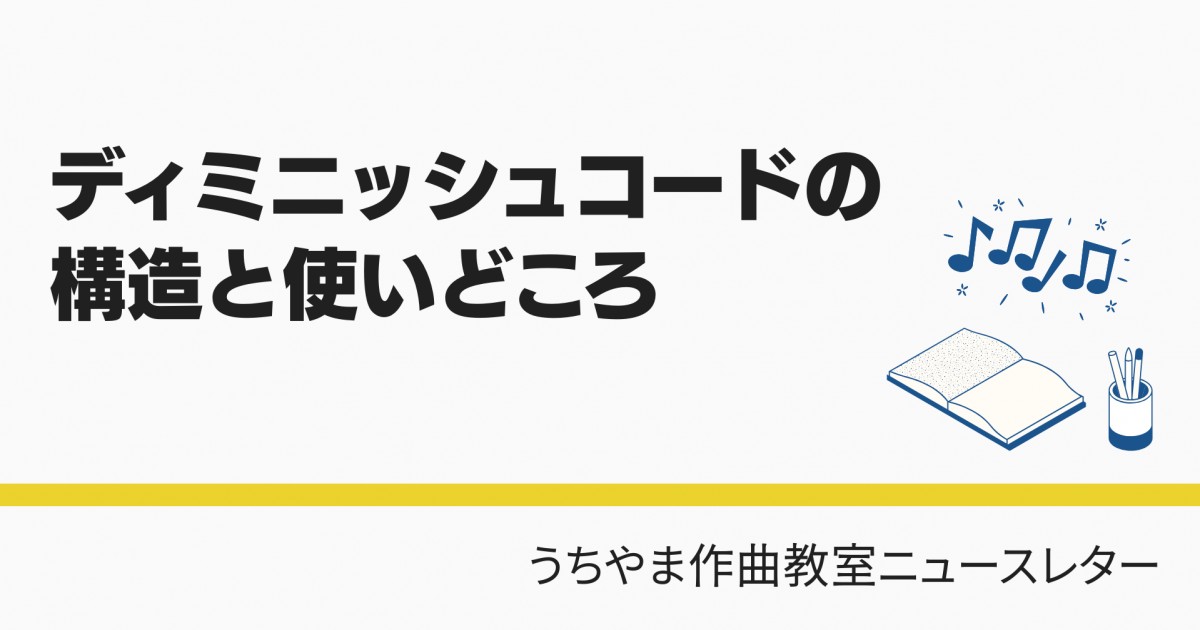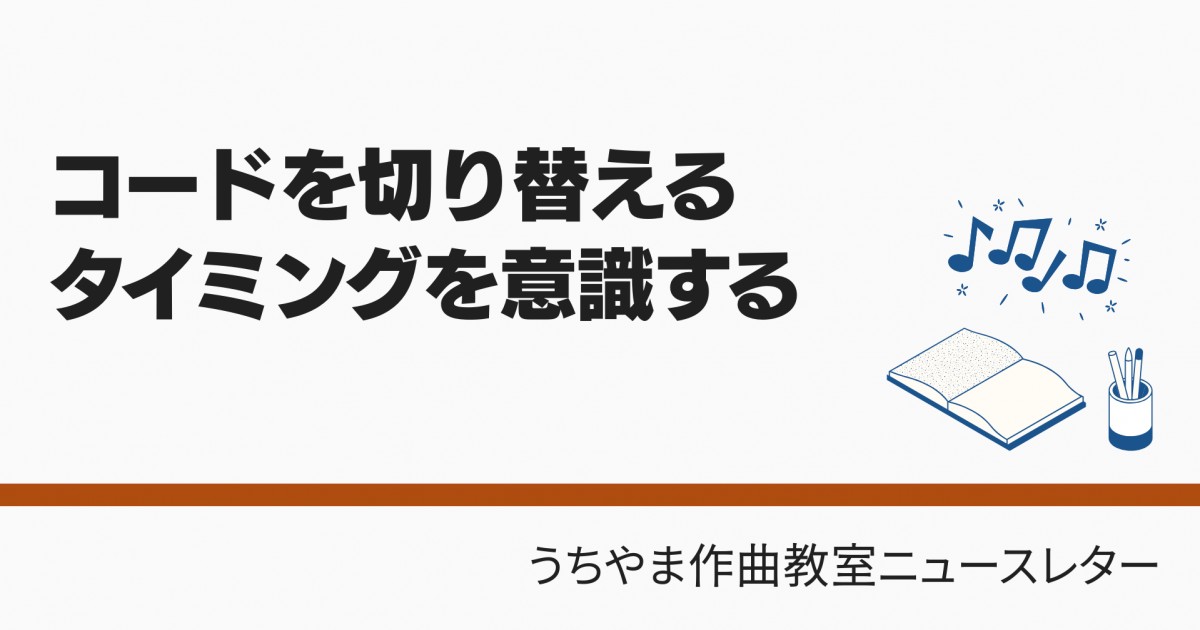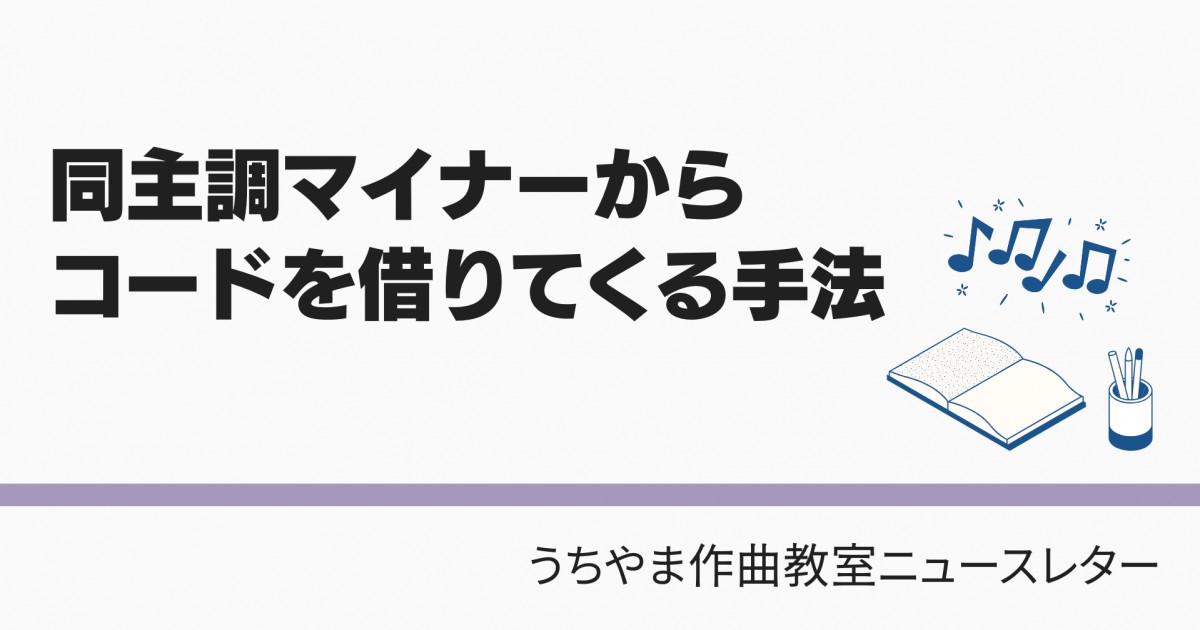いまいちなメロディのチェックポイントとそれを回避するヒント
意識すべきは音の上下と多彩なリズム
内山敦支
2025.04.18
読者限定
内山です。今回は、メロディがいまいちなものになってしまう例と、それを改善するヒントのようなものを書いてみます。
***
メロディ作りに慣れていない初心者によくあるのが、作るメロディのほとんどが
-
同じ高さの音が連続する
-
「タタタタ…」と無計画に音を刻む
という状態になってしまうケースです。
意図してメロディがこの状態になっているのであれば問題ないですが、その多くは無意識で、結果としてそこからは動きが感じられず、聴き手の印象としても、また作っている本人の手ごたえとしてもメロディはいまいちな感じになってしまいます。
特に、メロディ作りの経験が浅い時期はこの二点に気を配るだけでメロディの質をある程度保つことができて、より具体的には、メロディを作る時に