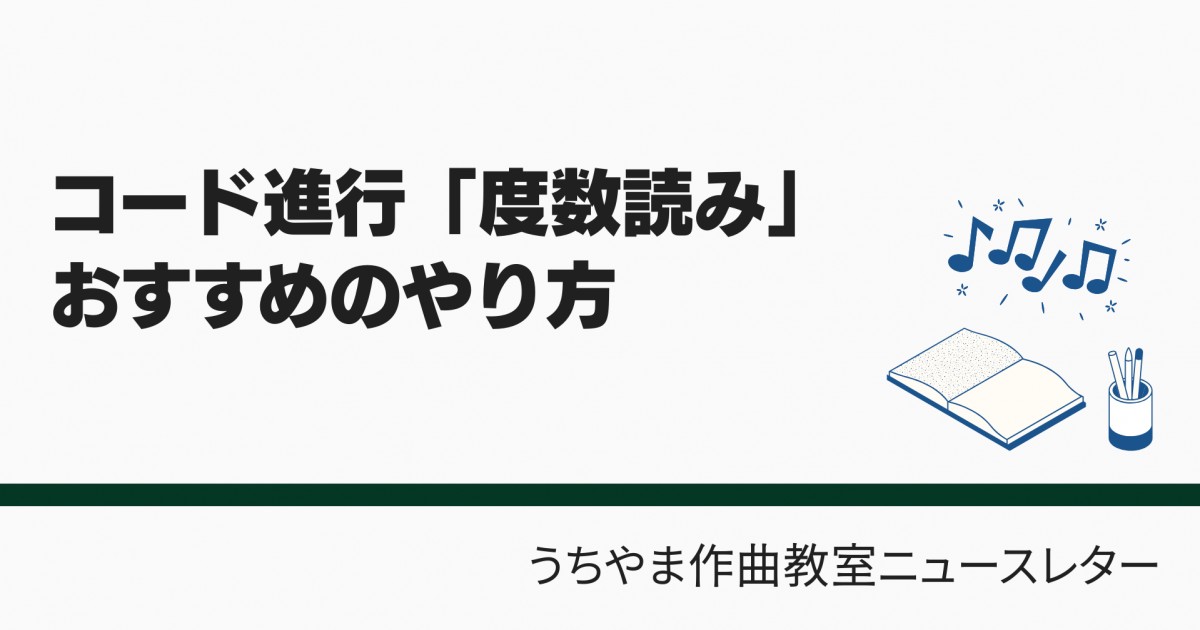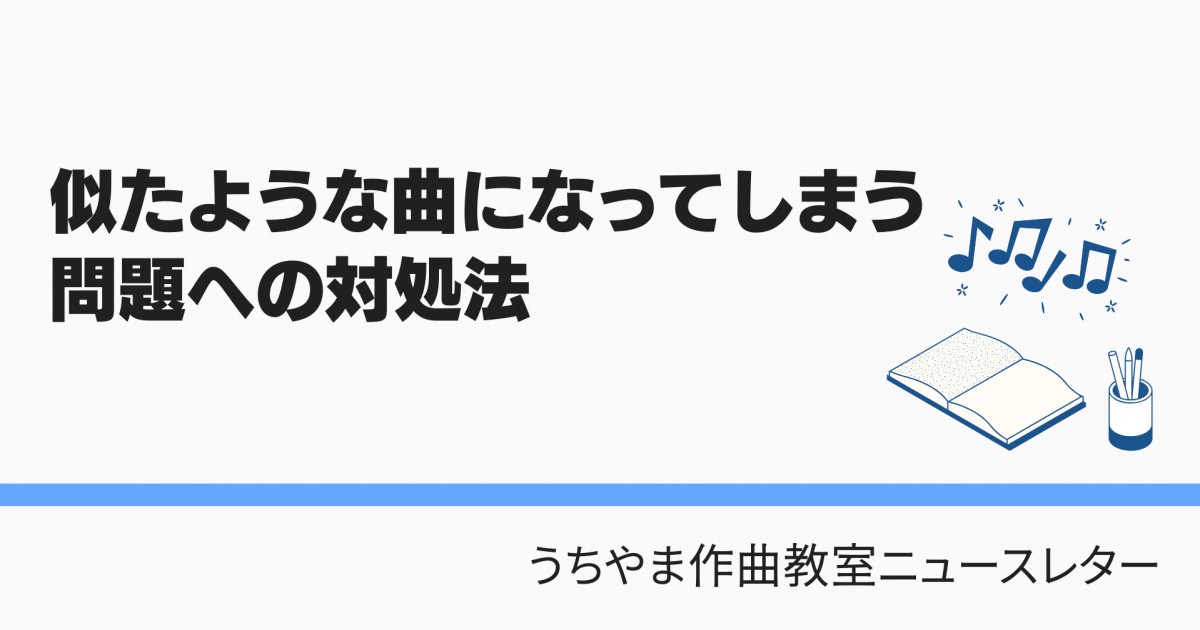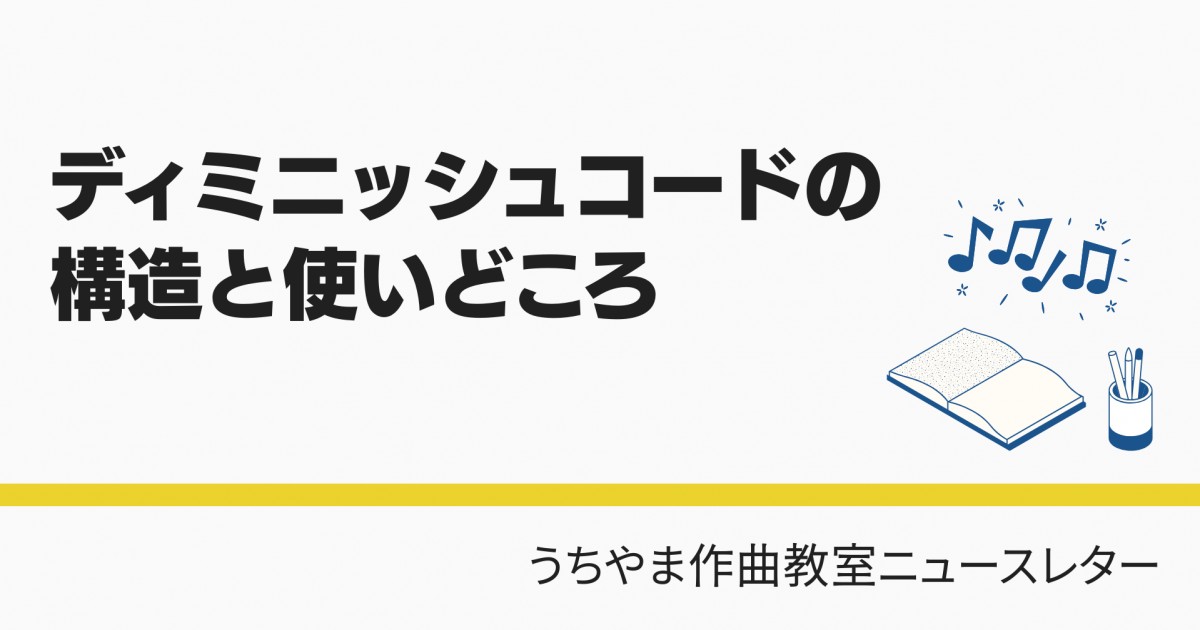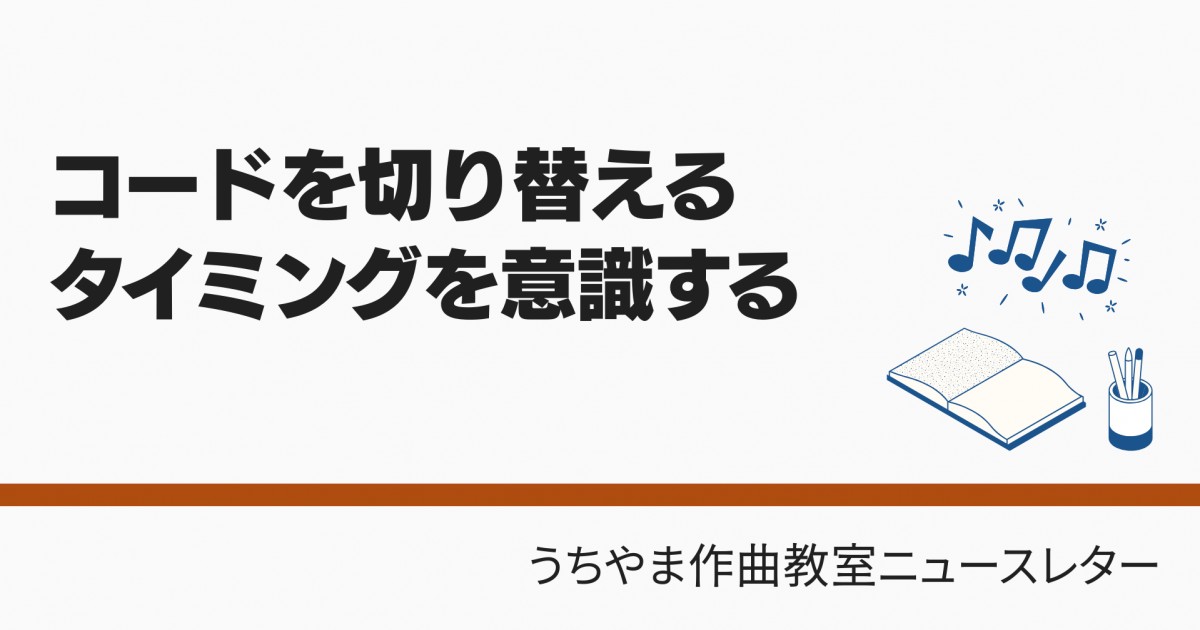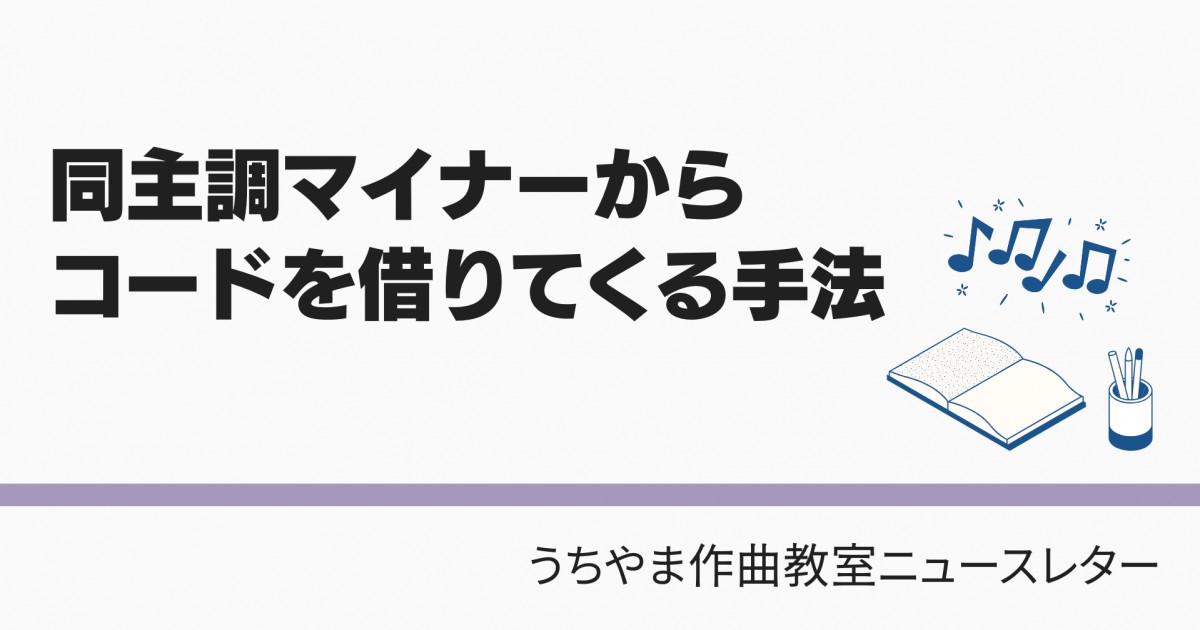分数コードの詳細や活用法など
分数コードの二つの分類と、代表的な三つの使用意図について整理します。
内山敦支
2025.06.26
読者限定
こんにちは。ギターでコードを演奏するときにベースのつながりのスムーズさを気にしたがる内山です。
今回は数あるコードの中でも少し特殊な部類に入る「分数コード」の詳細と、その分類や活用法などについてまとめてみます。
分数コードの概要
そもそも「分数コード」とは「C/E」のように表記するコード全般を指す言葉で、その見た目が「分子/分母」の形になっていることから「分数」という呼び名が付けられています。
一般的な「C」や「Am」などのコードは、大文字アルファファベット部分がそのコードの土台となる音(=ルート音)を意味しており、コードを表現するうえでもルート音がそのままベース音になります。
例えばコード「C」は、大文字アルファベット「C=ド」がルート音であり、それをそのままベース音としても活用することで、
-
コード構成音「ド・ミ・ソ」
-
ベース音「ド」
として表現されます。
一方でこれが、例えば分数コードの「C/E」では、スラッシュの左側にある「C」をコード、スラッシュの右側にある「E」をベース音と解釈して、
-
コード本体は「C(ド・ミ・ソ)」
-
ベース音は「E(ミ)」
のように表現されることになります。
この記事は無料で続きを読めます
続きは、6374文字あります。
- 分数コードの分類:転回形になる/ならない
- 分数コードの使用意図(ベースのつながりをスムーズにする)
- 分数コードの使用意図(ベースの動きを止める)
- 分数コードの使用意図(「V7」に近い響きを生み出す)
- まとめ
すでに登録された方はこちら