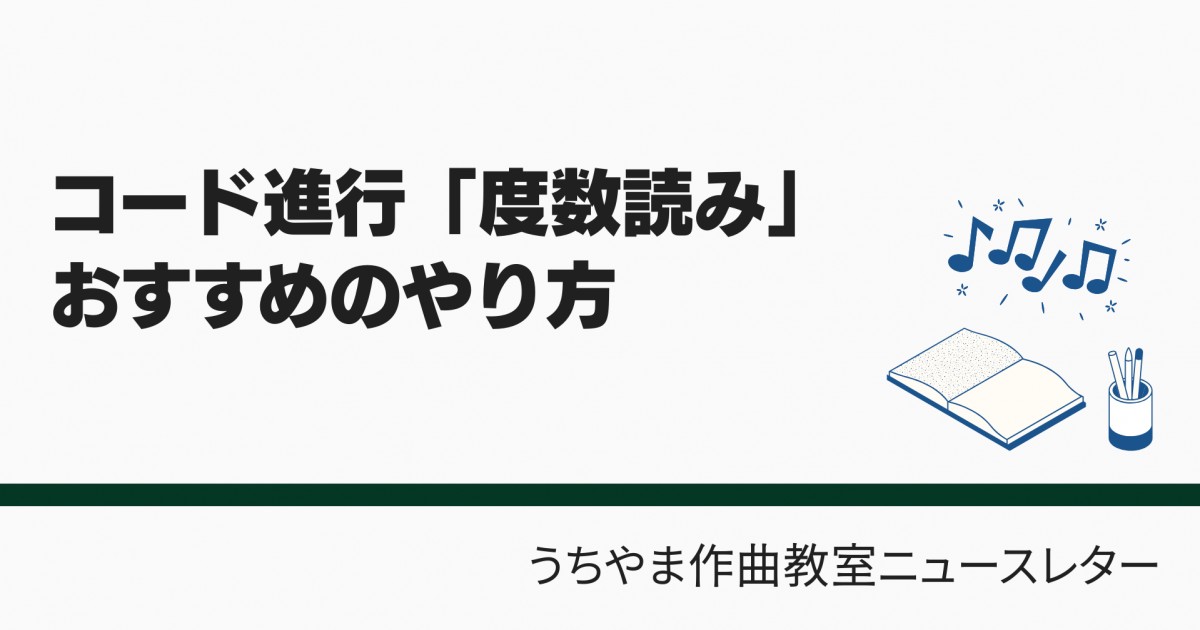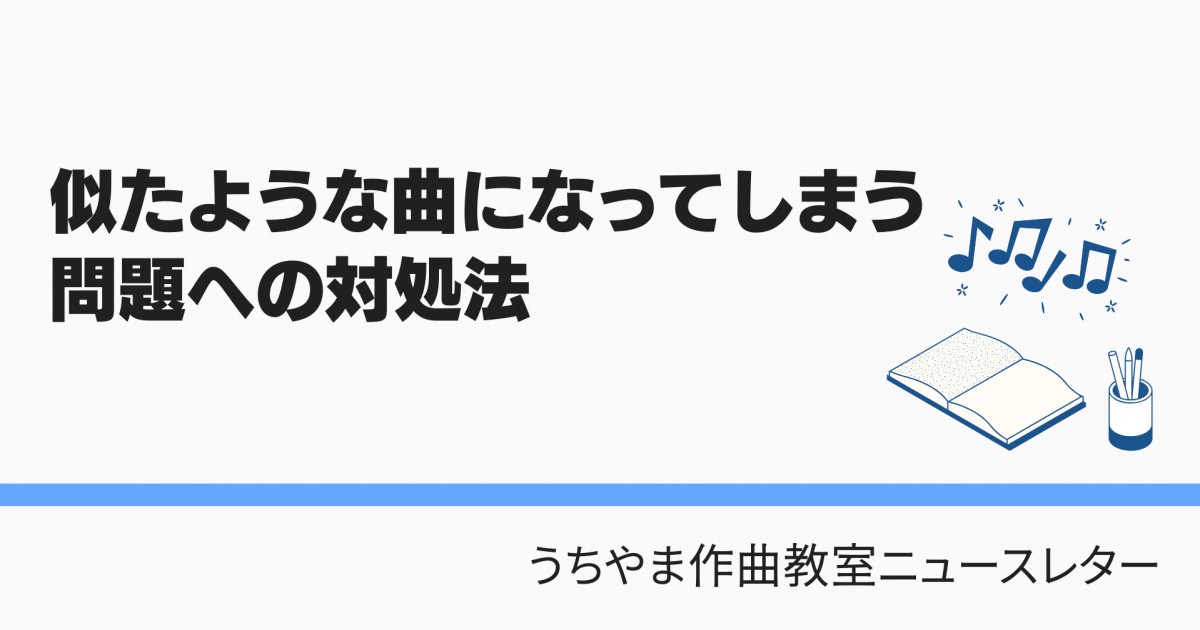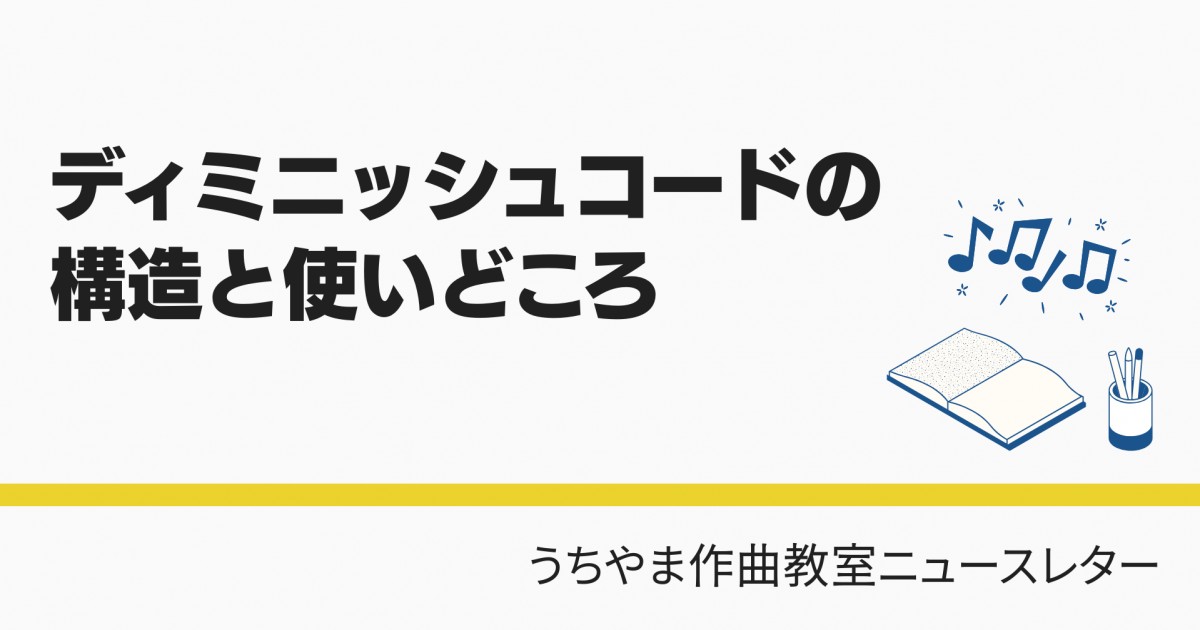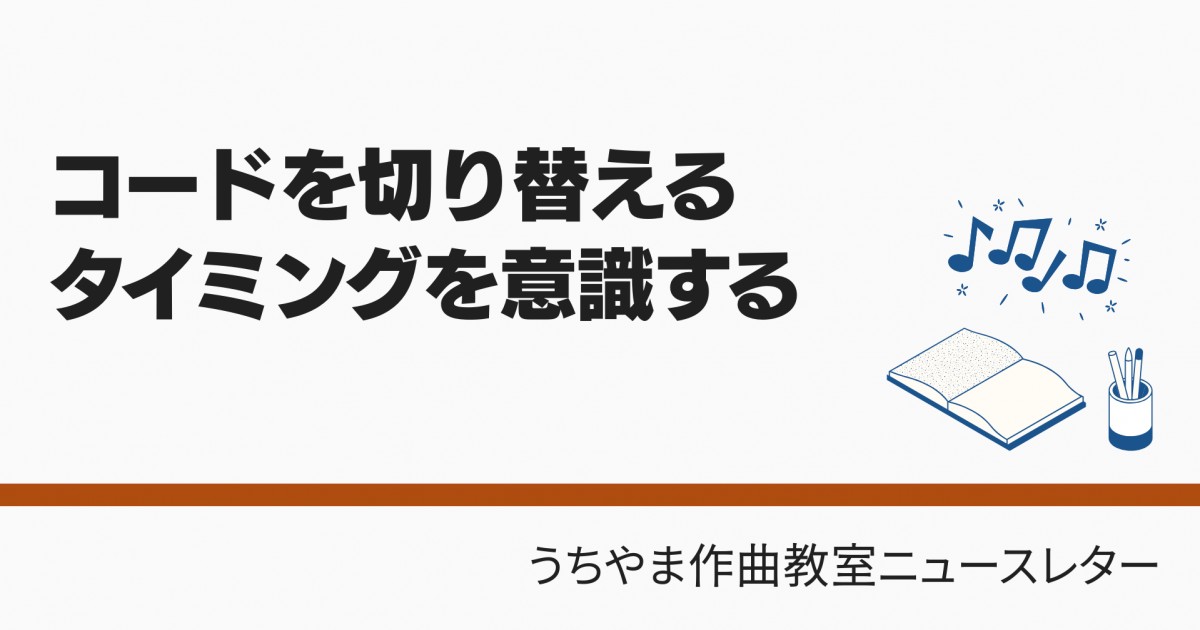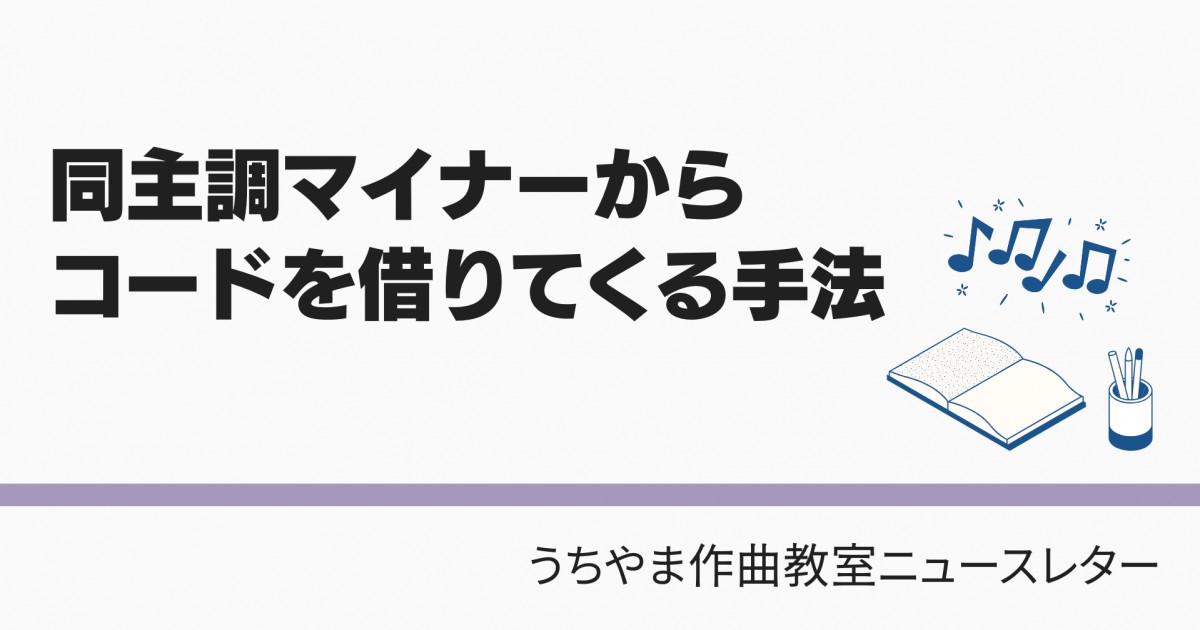メロディの音がどう進むかという構造的解釈
内山です。こちらのニュースレターも今回で3回目の配信になりました。私が想像していた以上に多くの方に見ていただけていて、とても嬉しく思っています。皆さんの日常的な作曲活動のヒントや支えになるような内容をマルチトピックのスタイルとして柔軟にお届けしていきたいと思っているので、今後もよかったらお付き合いください。
メロディの「音の進め方」について
3回目の配信となる今回は、メロディ作りに関する少しマニアックで、それでいて良いメロディ作りにつながるような内容について解説をしてみます。
メロディ作りが得意な人はなにげなく鼻歌を歌うような感覚で、オリジナルなメロディをすらすらと生み出せてしまうものですが、その点に苦手意識がある人からすると、どういった発想でメロディを生み出せばいいかもわからなくなってしまうものです。
特にボーカル曲の場合は歌うことがメロディ作りの中心的な作業になるため、意識せずにそれを行おうとするとすべてが似たようなメロディになってしまったり、それなりに個性的で聴きごたえのあるメロディを生み出すことは案外難しかったりします。
そんな時に第1回目のニュースレターでもお伝えしていた「モチーフ」の概念のようなメロディの構造に意識を向けることは効果的で、中でも「音の進め方」への配慮は特別な知識を必要とせず、それによってメロディの雰囲気を大きく操ることができます。